




従業員を雇用する全ての企業が対応が必要!2024年4月1日~労働条件明示のルール変更
2024年4月1日~労働条件明示のルールが変更になりました。 今回のルール変更は・・・
MORE

「賃上げ実現に向けた福岡県中小企業生産性向上緊急支援補助金」の募集が開始されました!
「令和5年度・令和6年度賃上げ実現に向けた福岡県中小企業生産性向上緊急支援補助金・・・
MORE


「賃上げ実現に向けた福岡県中小企業生産性向上緊急支援補助金」の募集が開始されました!
「令和5年度・令和6年度賃上げ実現に向けた福岡県中小企業生産性向上緊急支援補助金・・・
MORE

医療機関向け経営情報誌「季刊CMSwithアップパートナーズグループ No.13」を発行しました
この度、「季刊CMS withアップパートナーズグループ」No.13を発行いたし・・・
MORE




「経理と総務から始めるデジタル化セミナー」に福岡オフィス所長鈴木が登壇します!
クラウド会計ソフト「勘定奉行」などを展開する㈱オービックビジネスコンサルタント主・・・
MORE



「OV-AN meet-up2024@福岡会場」にて、福岡オフィス所長の鈴木と渡邉が登壇します!
経営支援クラウドサービス「bixid(ビサイド)」を展開する、株式会社YKプラン・・・
MORE

「freee Advisor Day2024 in福岡」に弊社代表・菅が登壇します!
クラウド会計ソフトのフリー株式会社が主催する会計業界最大級のイベント「freee・・・
MORE


士業事務所規模総合ランキング全国44位、会計事務所規模ランキング27位になりました!
メディア掲載情報のお知らせです。 士業専門誌「FIVE STAR MAGAZ・・・
MORE







従業員を雇用する全ての企業が対応が必要!2024年4月1日~労働条件明示のルール変更
2024年4月1日~労働条件明示のルールが変更になりました。 今回のルール変更は・・・
MORE











お客様のあらゆる経営課題に
ワンストップで対応いたします。
アップパートナーズグループは大切なお客様の未来をともに創造していくことを目的に、税務や人事労務、事業承継、資産運用など、あらゆる経営課題にワンストップで対応する西日本最大級のコンサルティングファームです。
事業規模や業種・業界を問わず、お客様1社1社の信頼できるパートナーとして、豊かな未来を創造していくための各種サービスをご提供いたします。
税務・会計・相続
お客様の未来を創るパートナーとして、税務・財務・会計を総合サポートいたします。
人事・労務
企業に、ここちよい風を。経営者の思いと労使のバランスを重視する、人事労務のエキスパート。
コンサルティング・IT支援
未来創りを支える。経営者の想いに寄り添う総合コンサルティングパートナーです。
M&A
M&Aを通じて、大切な事業、そして想いを未来へつないでいくお手伝いをいたします。
一般法務・生前対策
相続・遺言・成年後見から登記業務まで。お客様の心に寄り添えるよう、丁寧なサポート対応が信条です。
保険・資産運用
お客様の豊かな将来に向けたターニングポイントとなれるよう、確かな保険と資産運用をご案内します。
相続手続代行
複雑な相続手続きを丁寧にご支援。初回無料相談は24時間予約受付中です。
事業の承継支援
長崎の事業承継やM&Aのご相談は昇継へ。180件以上の豊富な支援実績と経験から、オーダーメイドのプランをご提案いたします。
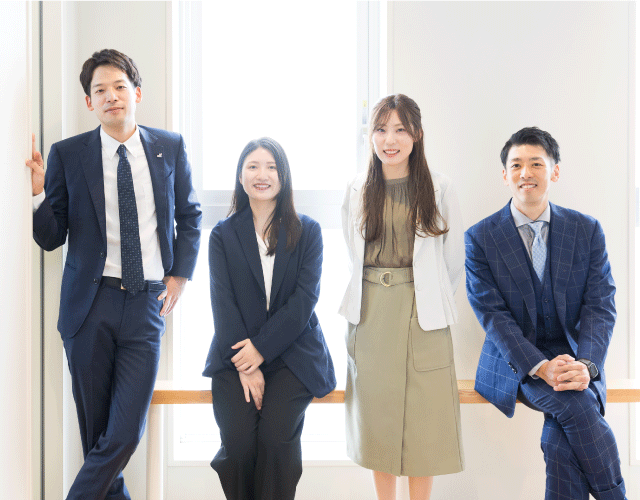
アップパートナーズグループでは、共にお客様の未来を創る仲間を募集しています。税理士や公認会計士、社会保険労務士、司法書士などグループ内にあらゆる分野の専門家がいるため、素早い情報収集と正確な知識でお客様のお困りごとに多角的なアプローチができるやりがいのある仕事です。「今の自分よりももっと成長したい」、そんな想いをもった方のエントリーをお待ちしています。
KITAKYUSHU北九州
〒802-0006 北九州市小倉北区魚町1-4-21 魚町センタービル8階
















